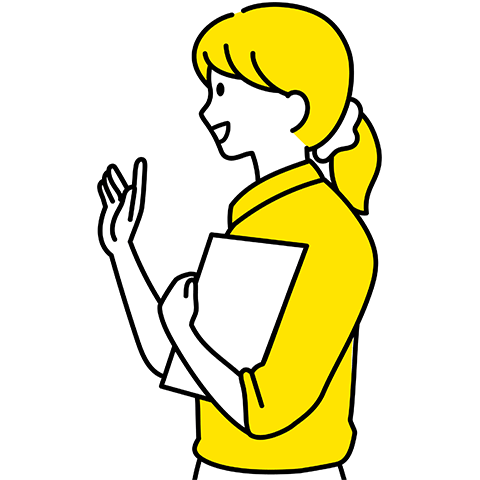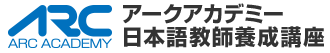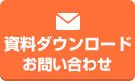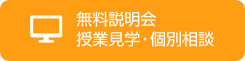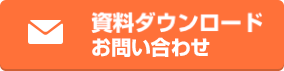No.197「あいさつ案件」を考える
2025/07/18
家の近くに区立小学校があり、たまたま下校時間に横断歩道のあたりを通ると、子どもたちを安全に誘導する「見守り」の人がいる。楽しそうに下校する小学生の姿は、いかにも「平和だな」という気分になれるのだが、ずっと気になっていることがある。その見守りの人たち(多くは小学生の祖父母世代)が小学生たちに「さよなら」「気をつけてね」と声をかけても、まるでそれが聞こえないかのように、返事がないのである。少なくともはっきりと「さよなら」と言う子どもはほとんどいない。
私はその横を通りながら、「あいさつはちゃんとしようよ!」と心の中で静かに嘆き、ごくたまに元気にあいさつしている子どもに会うと「100点満点!」と勝手に採点して心の中で拍手している。
というのも、これが他人事とは思えないからである。現在担当している準備教育課程の2クラスであるが、実に対照的なクラスとなっている。1つは落ち着きに欠け、何かきっかけがあると母語でおしゃべりが始まる。もう1つは盛り上がりに欠ける印象で、全体的におとなしい。まさに「足して2で割ってちょうどいいかもね」といった感じなのである。そして、後者のクラスに関しては「あいさつ」が、たびたび教師の間で話題になる。つまり、こちらの「おはようございます」に対する「おはようございます」という返事が、残念ながらなかなか聞けないのだ。おとなしいのは性格なので悪いとは言えないが、やはりあいさつに返事が返ってこないのは、何だかこちらも気分がよくない。
パソコンや電子黒板の設定などもあって、教師は通常早めに教室に入る。その段階ですでに登校している学生がいる場合は、まずそこで彼らに「おはようございます」と声をかける。そして、出欠をとる際も、一人ひとり名前を呼んで改めて「おはようございます」である。が、その際も元気にあいさつを返してくれる学生はあまりいない。これは私だけではなく、他の教師も同様であるらしい。
なぜそうなのか、ちょっと考えてみた。日本で重要とされているあいさつが、彼らの国ではそれほど重要ではないのだろうか。または「みんなの前で声を出す」というのが恥ずかしいのだろうか。彼らからすると「この先生、朝から妙に元気だな」ということになっていたら、ちと悲しい。または、単純にその日の授業のことを考えると憂うつになって、明るくなれないということかもしれない。そう言えば、彼らの中にも以前から、授業後に帰るときは笑顔で「先生、さようなら」と自分からあいさつして去っていく学生もいる。やはり、気分があいさつの有無を左右している可能性もある。
しかし、日本ではそのときの気分がどうであれ、あいさつは基本中の基本。学生たちが出会う人たちとのいい人間関係、いい環境を作るためのカギだ。一人ひとりはいい学生なだけに、実にもったいない。来年3月の卒業までにこの案件を解決すべく、今後もしつこく努力を続ける所存である。