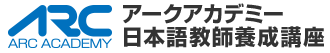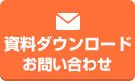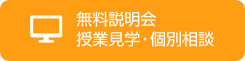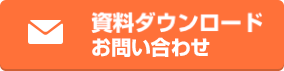【卒業生インタビュー/海外勤務】~ドイツで日本語を教える~
2025/08/06

西川 伴子さん
420時間総合コース
2023年10月期生
2024年の9月から2025年の5月まで、海外教育交換プログラム(インターナショナル・インターンシップ・プログラム主催)を利用して、ドイツのギムナジウム(大学進学をめざす、小学5年生から12年生あるいは13年生までの生徒が通う一貫校)で日本語を教えてきました。
このプログラムは、現地の生徒に日本語や日本文化を紹介しながら、その国の教育を多方面から観察・体験するとともに、ホストティーチャー宅でのホームスティなど日常の中で交流をはかる海外研修です。現職教員あるいは教員経験者が応募でき、立場としては研修生で、無償ボランティアです。私は大学でドイツ史を学んだので、かねてからドイツの教育現場を経験することを希望していました。そこで、2023年の10月から半年間、アークの養成講座で学んでから、このプログラムに参加しました。参加には日本語教師の資格は不要ですが、現地に赴いてみて、養成講座で学んでおかなければ、現地の優秀な生徒たちに教えることはできなかったと思いました。
1. アークの養成講座で学んでよかった点
① 駅チカで便利なアクセス
新宿駅から4分ほどのアクセスは、毎日週5日通うのに、大変便利でした。満員電車にゆられてたどり着くと、受付のスタッフの方がいつも素敵な笑顔で迎えてくれました。
② 個性豊かな先生とたくさんの学び
いったん教職についてしまうと、多忙のため新たな分野を系統的に学ぶ機会はなかなかありません。個性あふれる先生方が熱心に教えてくださり、その姿勢や内容が私にはとても新鮮でした。「教えるために学ぶ、学ぶと教えたくなる」の好循環が再びまわり始めました。様々な指導法を学び視野が広がったことが、ドイツの授業でも役立ちました。
③ 仲間は一生の宝物
正直言って、苦手な分野や教育実習ではつらく感じることも多々ありましたが、異なる世代の同期の仲間と励まし合いながら、乗り越えました。この仲間とは、今もつながっています。
2. ドイツでの授業
現地の言葉を使って独自にパワーポイントを作成し、電子黒板を使って教えていました。選択授業「日本語」の生徒たちは、少なくとも英語、ラテン語かフランス語を学んでいて外国語に慣れていました。そこで、文法の構造は論理で理解したいタイプだと考え、文型や例文を日本の文化と関連付けて作成し、練習・復習をしていきました。文字(ひらがなとカタカナ)や単語の定着は、かなり個人差がありましたが、カルタ遊びや、「あっち向いてホイ」などのゲームを取り入れながら、 飽きさせずに体を動かして覚えられるように工夫しました。日頃から日本の文化(特にアニメやマンガ)、スポーツ(空手、柔道)、日本食(寿司、米)に親しんでいる生徒が多く、さまざまな文化体験(折り紙、書道、料理など)を含め、楽しみながら取り組んでいました。私のドイツ語力の拙さは、生徒が助けてくれました。

スーパーマーケットの寿司売り場
また、選択授業の他に、日本に留学予定の高校生に 『みんなの日本語』を用いてプライベートレッスンをしていました。日本語とドイツ語両方からこの教科書に向き合ったことは、私にとって大変勉強になりました。日本にいる時は、内心、古い内容のテキストだなぁと思っていましたが、実にうまく構成されていることがわかりました。
3. ドイツでの生活
滞在先がかなり田舎だったので、移動手段に苦労しました。毎日、学校までアウトバーンで30分弱、ホストティーチャーの車に乗せてもらって通い、帰りはバスで帰ってくることもありました。週末はそもそもバスがないので、もっぱら近くを散歩して過ごしました。冬には暖炉に薪を頻繁にくべるのが大変だったり、春には信じられない数のテントウムシが室内に入ってきたりもしました。でも、自然と共生し、環境にやさしく、宗教と結びついた暮らしは、めったに経験できない貴重な体験となりました。
学校は、デジタル化が日本よりもはるかに進んでいて、合理的に運営されていたので、日本の未来の学校を見ているようでした。その中で、本当にたくさんの先生方の授業を見学させていただき、授業後は可能な限り質問をしました。直説法による語学の授業はもちろん、歴史の授業も、生徒の発言が非常に重要視されていて、教員や生徒は、その発言に忍耐強く耳を傾けます。寝ている生徒は見たことがありませんでした。

教室の様子
外国暮らしは2度目でしたが、今回も日本の良いところを再認識し、その点では少しナショナリストになって戻ってきた感があります。言葉のディテールが聞き取れなくて、日本や自分の常識に沿って文脈を理解しているつもりになっていると、実は全く違って理解していたことがしばしばありました。ただ、いずれにせよ、多少の齟齬があったり、文化的背景が違ったりしても、人を思いやる気持ちには国境がないことも実感しました。この9か月間の体験を、今後は日本にいる学習者のために役立てていきたいと思います。

散歩コース