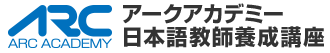用語名
明治・大正・昭和初期の日本語教育(国外)
めいじ・たいしょう・しょうわしょきのにほんごきょういく(こくがい)
用語詳細
サハリン南部・千島列島・北海道・本州東北部に話者が存在していたアイヌ語は明治政府の同化政策により結果的に話し手の激減を招いた。明治政府は国外に対しても植民地化を進めそれぞれの地で日本語教育が行われ、この時期の日本語教育には当時の統制的な姿勢が影を落としていた。
日清戦争(1894 - 1895)後,日本が領有することになった台湾での日本語教育が1895 年伊沢修二(音楽教育者 1851 − 1917)により始まる。国語学校で山口喜一郎(1872 − 1952)らがグアン法(Gouin Method)を研究し教授法とした。
日露戦争(1904 − 1905)は満州と朝鮮の制覇権をかけた戦争で、戦争後日本は朝鮮を治めることになった。教育課程のなかで日本語を必修科目とした。
第一次世界大戦後(1915),南洋諸島(ミクロネシア,サイパン,ヤップ,パラオ,トラック,ポナペ,ヤルートなど)が日本の統治下にはいり,ここでも日本語教育が始められた。
その後,満州事変(1931)を経て,1934年には満州帝国が成立し,ここでも日本語教育が行われた。しかし、中国大陸部での日本語教育はさまざまな問題を露呈させた。
真珠湾攻撃(1941)から太平洋戦争の初期は日本は勝ち進み,南洋諸島,東南アジア全体に戦争は拡大した。太平洋地域への日本語普及策は脚光を浴びた。
それらもすべて敗戦によって終わりを告げた。
検索インデックス
検索カテゴリー